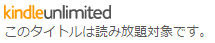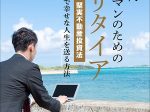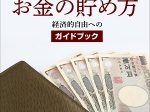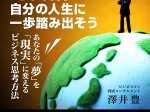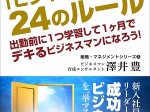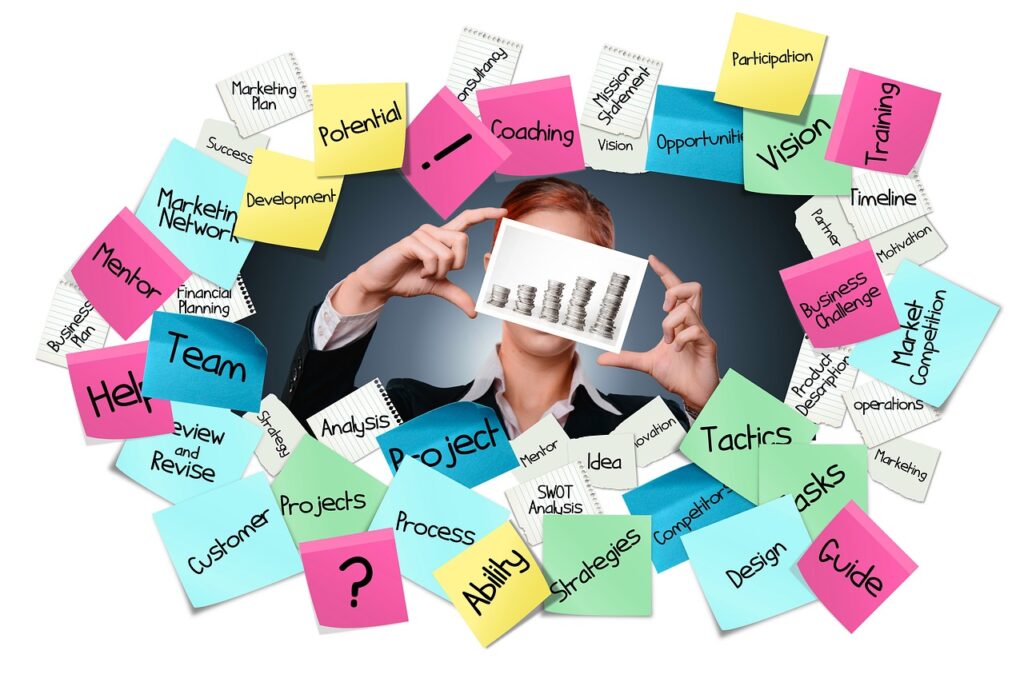
大手スーパー/ショッピングモールなどが進出してきたことで、昔から細々と経営してきた地元のお店がやっていけなくなる(潰れる)・・・という話はよくあります。
同じようにA地点からB地点へ行くにはその道を通るしかなかったのに、高速道路や幹線道路ができたので従来の道を利用する人(車)が減り、その沿線にお店を出していたところが廃れていく・・・という話もよくあります。
「黙っていても顧客が毎日店の前を通る」という状況が、ある日を境にパタッと客足が途絶えてしまう・・・というわけです。
これは誰が悪いとかではなく、単に「構造不況」によるもので、言い換えれば「外力」によるものです。
外力に対して自分の力量でどうこうしようとすることを「内力」と呼ぶなら、内力だけでは効力はぜい弱です(負けます)。
競争をするなら、「内力+外力」で競争するほうがベターです。
これが時代の変化に「適応する」ことにつながります。
・・・・・・・・・・・・
これらの話を拡大解釈していくと、「内需」の話になります。
人口の多い国では何もしなくても自国向けのサービスで簡単に稼げます。
高度成長期の日本がまさにこれでした。
国民の平均年齢が若く、発明と発展が同時だった時代は、放っておいてもモノがどんどん売れるだけの消費活動が存在していました。
ところが、経済の成熟とともに徐々に人口が減っていくとそうしたことは失われていきます。
「高度成長期の概念や思考」で同じように稼げ続けるわけがありません。
「どうして昔ほど稼げないんだ!」と愚痴っても仕方のないことです。
自助努力だけでは拭いきれないものがあり、外部環境の変化に自分も変化して適応していくしかありません。
構造が変わった以上は、商売のやり方を変える必要があります。
たとえば、「(内需の方向ではなく)世界向け」にサービスを展開する・・・とか、「国内顧客の総取り」でいく・・・とか、それとも商品・サービスの内容を変える・・・などです。
展開を世界目線に変えることはなかなか容易ではないし、「顧客の総取り」も現実的ではありませんが、いずれにしても、さまざまな試行錯誤が求められます。
また、今、なかなか思うように発展・繁栄しない環境だとしても、いつの日か反転してうまくいく日が来るかもしれません。
ビジネスでは「いつまでも続くと思うな、今の外部環境を・・・」という認識を持っておくことが大事です。
それは良きにつけても悪しきにつけても・・・です。
そんなリスク管理の姿勢と経営意識をもって長期的視点に立ってビジネスを展開することが大切だと思います。