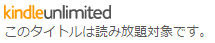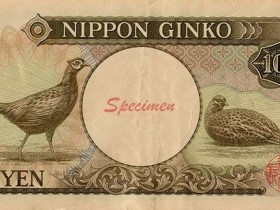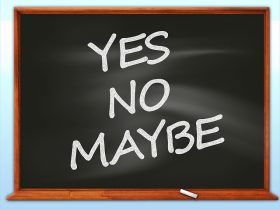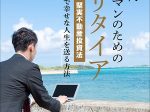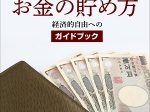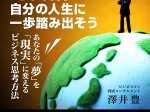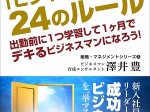自由人の歴史は、偶然ではなく 彼らの「選択」によって書かれる
by アイゼンハワー(アメリカ第34代大統領)
・・・・・・・・
経済の変化は、人間の感覚や文化をじわじわと塗り替えていくと言われます。
子どもならともかく、いい歳をした大人であれば「茹でガエル現象」に嵌ってはいけないと思います。
*茹でガエル現象
生きたカエルを熱湯に入れるとカエルはその熱さに驚いて飛び出して逃げるが、水に入れた状態で常温からゆっくり沸騰させていくとカエルは水温上昇の危険を察知できず、そのまま茹でられて死ぬ・・・ということに基づいた比喩話の警句。
人も、緩やかな環境変化下においては、そのことに気づかず致命的な状況に陥りやすいものです。
しかし、そうは言っても人は自分がどんな状況に置かれているのか気づけません。
知らず知らずのうちに茹でガエル現象に陥って、「気がつけば誰もが貧乏を当然だと甘受して」いたりします。
たとえばコンビニのおにぎりの値段はいつしかじわりじわりと値上がりして今では普通に200円前後で売られています。
(一昔前であれば100円程度で買えていたのに・・・)
バナナ一房200円・・・リンゴ1個300円・・・タマゴ1パック300円・・・というのも今では普通になってきました。
昔は「〇〇円だったのになあ・・・」と嘆いたり悲しむのではなく、そうした環境の変化・経済の変化に適応し、自らの意思で主権を手にして生きていく姿勢が大切だと思います。
・・・・・・・・・・・・・
人は十代の頃、何らかの受験を経て形式的には自分が選んだ学校へ進学し、その後、社会人になるとき自分が選んだ働き方で巣立っていきます。
これらの表向きは「自分が選んだ」形になっていますが、実際のところは「(誰かに)選んでもらった/選ばれた」といっても過言ではありません。
自分で選んだはずの会社・就職先さえも、場合によっては「その会社に選んでもらった」と言えます。
そうした「選んでもらう生き方」が長く続くと、いつしか受け身の姿勢が当たり前になり、常に受動的な生き方になってしまいます。
一部の先見の明がある人はこれを逆転し、能動的な姿勢で自分の意思で選んで進む・・・という生き方に転換しています。
人生を「選んでもらう側」で終わらせるか?
それとも「自ら選ぶ側」になるか?
私は、人生の後半になるほど後者になっていくことが大事だと思いますし、そうした「選ぶ側」に立つためには、経済的な主権を手にすることが求められます。
だからこそ余計に「経済的自由を得る」という意識が大事ですし、自分の収入・資産を自分でコントロールできる力を持つことが大切だと思います。