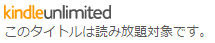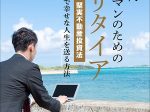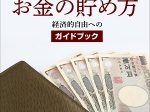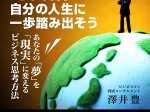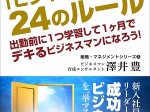9月は多くの会社で中間決算の時期です。
経営では「何となく経営していたらこの数字になりました」ではなく、「もともとこの数字を目指して経営してきた結果、こうなりました」という決算発表が大切です。
なぜなら、それが「有言実行」につながり、有言実行=約束を守る(守ろうとした姿勢)こそが「信用」になり、ひいては総合的にそれらが「経営手腕」として評価されるからです。
・・・・・・・・・・・
今期の数字(決算)をどう目標立てるか?も大切ですが、もっと先を見越して3年後、5年後、10年後の数字をあらかじめ想定した経営を行なうことも重要です。
そして、言えるのは「1年後の数字よりも3年後の数字のほうが大事」であり、さらには「3年後の数字よりも5年後の数字のほうが大事」であり、もっと言うと「5年後の数字よりも10年後の数字のほうが大事」・・・ということです。
短期の数字目標よりも中長期の数字目標のほうが大事になってくるのは、それだけ長い期間に渡っての先読みができること自体が企業存続において重要になってくるからです。
中期経営計画は大切ですが、その重要度は長期経営計画に劣ります。
聞いた話ですが、アイリスオーヤマは中期経営計画を公表したくないから敢えて株式上場をしないと公言しているそうです。
味の素は2023年に中期経営計画を廃止したそうです。
日立製作所は2019年に中期経営計画で売上高や利益の目標を掲げるのをやめ、事業間の連携で成長を目指す戦略に軸足を置いた・・・とか。
大企業の中でも短期・中期の数字よりも長期の数字を重要視しているところが増えてきているようです。
経営者として何年後まで見るのが正しいのか?は一概に言い切ることはできませんが、一つの目安としてはやはり「10年後」くらいに置くのが良いと思います。
なぜなら、自分が経営者として手腕を発揮する期間はせいぜい10年程度に留めるのが良いと思うからです。
経営者(トップ)でいる期間が10年を超え、長く君臨するのはあまりうまくないと思います。
3年~5年間の会社の進むべき方向性を明示することは良いことです。
3年~5年程度の中期経営計画を策定すること自体はたいへん素晴らしいと思いますが、1年~3年程度の目標達成を優先するあまりに長期目線での取組みが疎かになるのはうまくありません。
経営者は「3年後/5年後」より「10年後」を見据えて経営の舵取りを行ない、同時に自分の進退も検討するくらいの意識を持つと良いと思います。