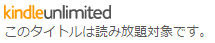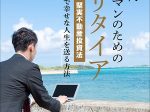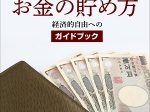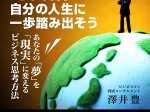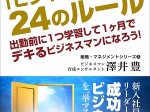焼肉屋さんで「カルビ」と言えば、牛肉のアバラ周辺のお肉(=バラ肉)のことを言います。
スナック菓子で「カルビー」と言えば、1949年4月30日に誕生した菓子メーカーのことを言います。
両者の言葉は非常に似ていますが、まったく関係はありません。
カルビ → 韓国語で言うバラ肉の意味
カルビー → カルシウムの「カル」とビタミンB1の「ビー」を組み合わせた造語
・・・・・・・・・・・・・
ジョンソン・エンド・ジョンソンで代表取締役社長、最高顧問を歴任した松本晃氏が2009年6月にカルビーに招聘され、代表取締役会長CEOとなりました。
当時のカルビーは非常にコストの高い会社だったそうですが、社内では「コストが高い=利益率が低い」ということに無頓着だったそうです。
そして、コストが高くなっている主な原因は、工場を造りすぎていたから・・・だったとか。
国内に工場は17ヶ所もあり、工場が多すぎると言わざるを得ないのは、当時の稼働率が60%程度という低さだったからです。
60%の稼働率というのは、一週間の稼働日である5日のうち3日しか稼働していないのと同じ意味です。
週休2日制のサラリーマンが、なおかつ週に2日欠勤しているようなものです。
会社側にとっては喜ばしい状態でないことは確かですが、データでそれを見抜く人が当時はいなかったのだと思います。
そうやって原価コストが高くなると、それだけ末端の商品価格も高くなります。
当時、松本会長はまずは変動費に手を目を付けたそうです。
それまでは余計なものをいっぱい買って、結局は使わずに廃棄していたものも多く、その無駄なコストを削るために、極力余計なものは買わないようにし、また設備投資も抑えたそうです。
やがて変動費は下がっていき、この下がった分の変動費をお客さまに全部還元する・・・という発想で、つまりは商品価格を下げたそうです。
その効果はてき面だったようで、ポテトチップスのシェアで見ると、57%だったのが75%くらいまでに上がったそうです。
シェアが上がれば自然と工場の稼働率も上がり、60%だった稼働率は今では90%を超えるにまで至ったそうです。
また、工場の稼働率が上がるということは、全体では固定費が下がることにつながり、固定費が下がればその分だけ利益率が上がります。
実際、固定費は10%下がり、わずか1.5%しかなかった営業利益率は、今では11.4%ににアップしたそうです。
・・・・・・・・・・・・・・・・
かつてのカルビーは「甘い」会社でしたが、松本会長はカルビーを「厳しいけれども、あたたかい会社」に変えたわけです。
ここで言う「厳しい」とは、プロスポーツ選手のようにキチンと「成果・結果を出す」ということです。
「あたたかい」と言うは、「社員一人ひとりが成果を出せるように、会社が環境と制度を整えて仕組みや文化を変えてあげること」です。
野球で3割打っても・・・ゴルフで優勝しても、まったく報酬・賞金が上がらない(もらえない)ようだと誰も一生懸命にプレーしようという気にはなりません。
同じように、会社でどんなに売上や利益に貢献しても、他の社員と均等割された給料・賞与だと誰も一生懸命働こうとしなくなります。
環境と制度を整えて、仕組みと文化を変えれば、社員は成果を出せる!・・・と言えます。
アメとムチ・・・ではありませんが、厳しさの裏では優しさ・温かみが大切です。
昔、仮面ライダースナックのお菓子をよく食べものですが、最近はすっかりスナック菓子自体を食べなくなっていました。
でも、こうしたストーリーを知ると、不思議とまた食べたくなるものですね。