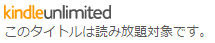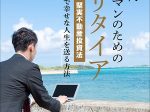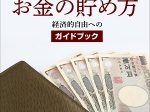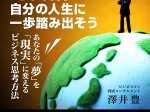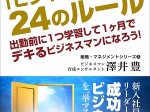親は、自分の子どもにいろんな期待をします。
〇〇を成し遂げてほしい・・・とか、△△になってほしい・・・とか、逆に▼▼にはなってほしくない・・・などです。
それと同時に、健康でさえいてくれれば何もいらない/笑顔で幸せに暮らしてほしい・・・とも願っています。
親がどう願おうと、結局は子ども自身が願ったようになるのがいちばん良いと思います。
なぜなら、子ども自身の人生だからであり、子どもと雖(いえど)も親がその人生をコントロールするのはお門違いだからです。
子どもが誕生してからある程度の期間、親は「子どもの先導者」です。
でも、それが一生涯続くとカン違いしてはいけません。
どこかで「子離れ」をする必要があります。
子離れをせず、いつまでも自分が「先導者」だと信じこむのは傲慢です。
「ひとつ(1歳)・・・ふたつ(2歳)・・・みっつ(3歳)・・・ここのつ(9歳)」と「つ」がつくまでの間は先導者ですが、「とお(10歳)」で「つ」がつかなくなる年齢になる頃、親はそろそろ先導者の役割を減らしていく姿勢が良いと思います(とうとう子離れの時期です)。
10歳を超えるあたりから徐々にその役割は弱まっていき、子どもが独立して親元を離れるようにもなればほぼ完全に先導者の役割は終えたと知るべきです。
ある時期からは「先導者」ではなく、「援助者(サポーター)」の役割に転換していくと良いと思います。
そうやって「親離れ/子離れ」をキチンとしていかないと、本当の意味で子どもの自立・独立は成り立ちません。
親が軸足をどこに置くか・・・子どもが進みたい方向に進めるように少しだけ支えてあげる・・・というくらいで良いと思います。
いずれにしても、「先導者としての役割」をしっかり果たしておかないと、子どもが歪んだ方向に進みかねないことは留意しておくのが良いと思います。