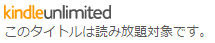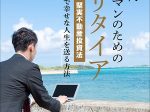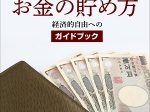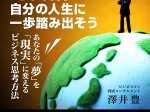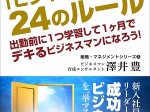東京では見たことがありませんが、昔、笠を被ったお坊さんが器を持って街角でお恵み(お金)を待つという、いわゆる「托鉢(たくはつ)」の光景を見たことがあります。
街角に立つだけではなく、一般家庭を戸別訪問していました。
子どもの頃、うちにも来ました。
そうしたとき、お坊さんは別にお金がありそうで裕福そうな家庭を意識的に訪問していたわけではないそうです。
教えでは、托鉢は裕福な家に限らず貧しい家をも等しくまわるのが基本だそうです。
どういうことか?
一般的に考えられるのは、貧しい家庭だと自分たちの生活に精一杯ですから他人にお金を施すという発想自体が起こり得ません。
しかし、お金でなくても何かを与えることはできます。
そこに実はとても重要なヒントが隠されていると思います。
今貧しいのは、与えないという考え方と行動があるために貧しいままにしている・・・という考え方です。
どんなに貧しくても、あるいは貧しくなくても、そうした「今の状態」には関係なく、常に心に余裕を持っていさえすれば他者に何かを与える(施す)ことはできます。
量が重要なのではなく、そうした気持ちと実際の行為自体(=質)が重要です。
そこで托鉢によってそんな貧しい人たちにも「他人に与える機会」をつくってあげて、ひいては今の貧しさから抜け出すための一助を為す・・・
これが托鉢の真の目的だと言われます。
自分の発想・考え方を改めることで今の貧しさから抜け出せるように手を差し伸べる・・・という実践はこうやって古くから行われてきました(残念ながら、昨今ではすっかり減ってしまったようですが・・・)。
托鉢は、そのお坊さんがお金を恵んでもらうことで自分がお金を得ることが目的ではありません。
そうしたことを通じて、「恵む」ということをした人が未来において幸せになれるように新たな道を示してあげることにこそ意義があるのだと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・
よく言われることに、「お金持ちになる人はお金持ちになる前から寄付をしたり、他人に何かを与えたり、授けたりする習慣が身についていた」ということがあります。
お金持ちになれる人は、先に与える、先に出すという考え方を持っています。
与える考えを持っているから、お金持ちになれるとも言えそうです。
もし自分がお金持ちになれたら寄付をしますよ・・・という人がいますが、お金があったら寄付をする(=お金がなければ寄付しない)という考えでは、たとえお金持ちになったとしても、もっとお金持ちになったら寄付をします・・・と言って永遠に寄付をすることはないと思います。
今の状態が大切なのではなく、今の気持ちがどうなのか、が大切です。
昔には街角で見られた托鉢も、今では熱中症や後継者が途絶える問題もあって見られなくなりました。
でも、温故知新の発想で学べることは何かとあるものだ・・・と思います。