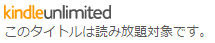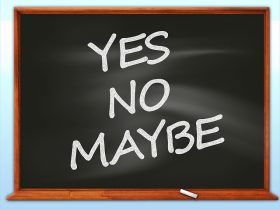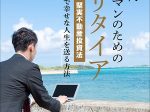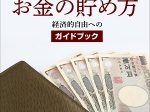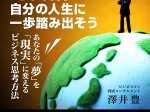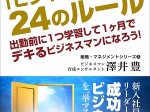資本主義社会においては、一番働いていない(とも言える)株主が最もお金持ちで、その次はちょっとは働いている役員がまあまあお金持ちで、その次はそれなりに働いている管理職がお金持ちと貧乏の狭間にいて、最後に最も働いてる従業員が実は一番お金持ちではない(人によってはかなり貧乏)という構図になっています。
これが現実社会の図式で、まあ、例外はあるにしてもそんなに大きく外れてはないと思います。
「社長は株主のパシリ、従業員は社長のパシリだ」・・・と揶揄する言葉は言い得て妙でもあり、あながち間違えてはいないと思います。
かつては、株主、役員、管理職、従業員はそれぞれ生まれたときからその身分がガチガチに決まっていて、自分の生まれた身分以外の身分に移ることが許されない、という感もありましたが、幸い今では努力次第でいくらでも移ることができる時代です。
一つの会社に関わる関係者としては、上記の4つに加えてもう一つ「顧客」という関わり方もあります。
(さらに言うと「取引先」という関わり方もありますが、)私は上記4つと顧客を含めた5つの関わり方が大事だと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・
話は戻りますが、資本主義経済社会では株主になることのほうが従業員になることよりも重要視されます。
資本家(株主)や資本家見習いには、一種の「労働否定(=従業員にならないこと)」の思考が大事になります。
ところが、人は誰でも株主になることはできませんから、場合によっては従業員として働きに出ることが好む・好まないに関わらず求められます。
また、そもそもの論理で言えば、奴隷制度ががない日本では、資本家(株主)に利益献上をしてくれる労働者(従業員)を増やす・育てることが必要で、そのためには昔から存在している「学校」が非常に役立ってきた・・・のかもしれません。
学校で学び(教育を受けさせる義務/受ける権利)、卒業後には社会に出て働き(勤労の義務)、そしてそこで得たわずかな賃金から税金を源泉徴収される(納税の義務)がうまく機能して課せられています。
知らず知らずのうちに、教育→勤労→納税までを一気通貫で行わされているわけです。
こうしたことを考えた昔の人はある意味では本当にスゴイ!と思います。
資本主義経済社会に潜んでいる裏の姿も、表面上見えていることと同じように理解をして、自分なりに把握しておくことは大切だと思います。