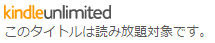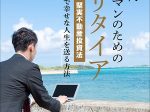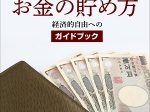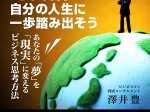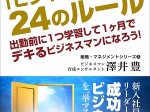「相続税を節税するため」の生命保険商品があるそうです。
相続税は、一定の資産を持つ人が死亡したときに遺族にかかる税金ですが、そのときの「相続税の額」は、その人が死亡した時点での財産評価額が基準になります。
生命保険は「死亡した本人が保険の対象」であればその「死亡保険金額」がそのまま相続税の対象になります。
ところが、その人が「別の誰かを保険の対象にして受取人は自分」という形で保険に加入していた場合、自分が死亡した時点での「解約返戻金」が相続税の対象になってきます。
ここで生じる「差」を活用するテクニックです。
以下、人から教えてもらった例ですが、こういった手法があるそうです。
たとえば、「本人が自分の子どもを対象に生命保険に入り、受取人は本人(自分)」・・・とします。
本人(自分)が死亡した時点での「解約返戻金」が相続税の対象になります。
ここで面白いのは、生命保険の中には「満期になれば多額の返戻金が出るのに、満期になるまでの一定期間はほとんど解約返戻金が出ない商品がある」・・・ということです。
たとえば15年満期の生命保険商品で、無事に満期日を迎えれば5,000万円返戻金をもらえるのに、14年目までに解約をすると返戻金はほとんどゼロに近い・・・といった商品です。
こういう商品が節税目的に使われたりします。仮に、この商品に保険料を全額分前納したとします。
すると、もし1年目から14年目までの間にこの人が死亡した場合、解約返戻金はゼロに近いため相続税の対象にはほとんど影響を及ぼさない(=生命保険の掛け金は相続税の対象とはほとんどならない)ことになります。
ただし、生命保険を前納した場合は加入期間が来ていない分の掛け金は、前払い財産としてカウントされています。
相続税の対象にならないのは加入期間が過ぎた分の保険料だけで、死亡した後の保険料は対象になってしまいます。
したがって節税目的でこうした生命保険に入ったものの、意に反して保険加入後早い時期に死んでしまうと、あまり相続税の節税にはならない・・・ということになります。
自分の死亡リスクが高い場合には節税になる期間が非常に短いという欠点がありますが、一考の余地はあるかもしれない手法かもしれないですね。