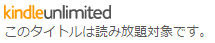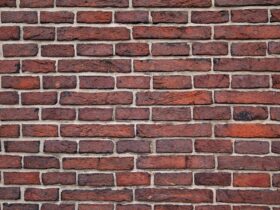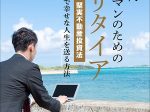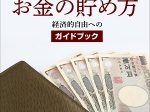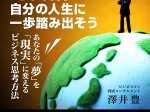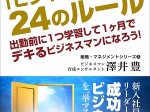P・ドラッカーはこう言いました。
未来のことは誰も予測できない。しかし、『すでに起こった未来』は体系的に見つけることができる。それは人口動態である。
・・・と。
・・・・・・・・・
日本では「人口減少/少子化」がときおりニュースになります。
年間70万人規模で今後減っていく・・・と言われていますが、もっと加速的に減少する恐れもあります。
1月末に発表された全国の転出・転入の数で見れば、「生誕人口」のみならず「転入人口」もほとんどの県で減少していて、結果として「人口減」となっているようです。
人口減少が何を意味するのか?
→ 人手不足 → 生産人口が減る → 暮らしにくくなる → さらに人が流出していく・・・のの悪循環です。
これを解決する一朝一夕の妙手はありません。
あればとっくに誰かがやっています。
短期目線で解決しようとするから答えが出ず、また浮かんだ案を実行しても(短期では)解決に至らないのだと思います。
長期目線で視て、長期運営で取り組むことでしか解決はしないと思います。
でも、そこまでの覚悟と理論武装をもって臨む為政者はいない(少ない)のだと思います。
なぜなら、為政者のほとんどは「50代以降」で世間で言う高齢者に近い層であり、もっと言えば人口減少は「自分には直接関係のない世代・年齢層だから」・・・。
変化はいきなり起きると人々は慌てますが、ジワジワと時間をかけて起きてくるとその変化自体に慣れが生じてしまうため、人々の焦りや恐れは弱くなります。
「茹でガエル」状態と同じです。
経営者/リーダーは、会社内でも「問題の先送り」とか「悪習慣の常態化」とか「茹でガエル状態」に陥っていることが多々あるかも入れない・・・と危機感をもってマネジメントにあたる意識が大切だと思います。