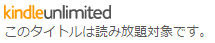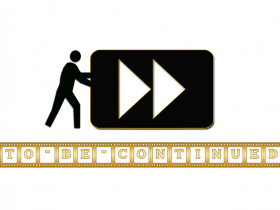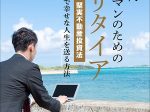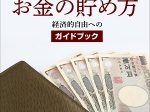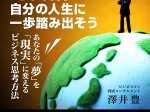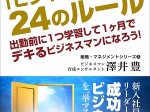私が現役時代に仕えた上司のうち、ある社長はこんな姿勢が特長的でした。
Q. 何か?
→ 「部下と議論しようとせず、部下の提案をいったんは取り入れようとする」ことを意識されていた・・・姿勢です。
おかげでいろいろ提案することができましたし、コミュニケーションもとても取りやすかった気がします。
・・・・・・・・・・・・
社員にやる気や自主性がないと嘆く経営者(社長)がついついやってしまっている誤ちがあります。
それは、「社員(部下たち)との議論およびその前半ですぐに部下の意見を否定してしまう」・・・ことです。
著書『人を動かす』で有名なデール・カーネギーは議論についてこう述べています。
「相手を議論で叩きのめすのは相手を傷つけたのと同じです。
傷つけられた相手はこちらの勝利を祝う気にはなりません。
ただ恨みだけを残すことになります」
多くの社長たちは「社員を大切にしています」とか、「何かあればすぐに言ってくれ」とか「改善・工夫の提案はいつでも大歓迎だ」・・・などと言って、社員の意欲・向上心を高めようとします。
ところが、実際に社員たちが何か意見を言おうとしても、その声を真摯に聞こうとせず入り口でピシャリ!と遮ったり、何らかの提案があってもそれを議論して否定路線で進め、どうにかして現状維持を図ろうとする社長が多くいます。
せっかくの社員からの具申であっても、それを無視するような形で社長が自分の考え・意見を非論理的に押し通した場合、社員のモチベーションは激下がり・・・です。
おそらく仕事へのやる気は下がり、社長を始めとした経営陣への不満が募ったり、会社そのものが嫌いになるかもしれません。
社長(経営陣)は「思いやりの心を持つこと」が大事です。
議論で部下を打ち負かすのではなく、部下に共感して理解を示すことがまずは大切です。
確かに「部下の意見はどう考えても間違っている」と感じることも多々あるかもしれません。
論理的に説明し部下が素直に納得できるような事例であれば構わないのですが、部下が論理的に納得できずわだかまりが残ってしまう/モヤモヤ感が残ってしまう・・・ようであれば、それなら思い切って部下の意見を取り入れてみるほうが得策です。
部下のモチベーションは上がりますし、失敗しても良い勉強になりますし、もちろんうまくいけば会社にとってメリットがあります。
部下の忠誠心や帰属意識は確実にその方が高まります。
部下と議論しすぎないで・・・、仮に議論しても頭ごなしに否定しないで・・・勇気を出して提案してきてくれた部下の意思を尊重する姿勢を見せることが大事だと思います。