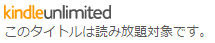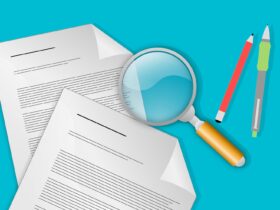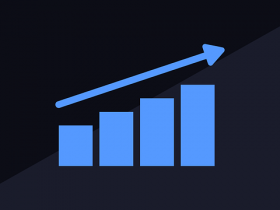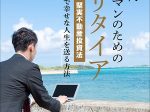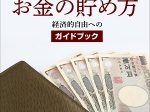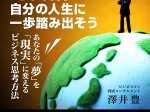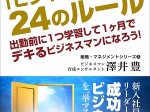昔、営業マンだったころ、他の営業マンと同じ勤務時間で他の営業マンの3倍以上の成績を収めていました。
例えて言うなら、チーム10人の目標を10としたとき、本来はそれぞれが「1」の成績を収めれば良いところ、私一人で「3」とか「4」とか「5」という成績を出していたわけです。
やがて、上の人は「これだったらチーム目標を10じゃなくて15にすればもっと業績が上がるぞ」と思い始め、途中で目標数値を上昇修正されることがよくありました。
私としては早々に実績を収めた後の時間を他のことに使いたかった・・・スキルアップとか、知識の吸収とか、見聞を広げるといったことに活用したかった・・・のに、その意見が通らなかったのは残念でした。
長期視点で全体を俯瞰して視ている私と、目先の数字だけに囚われて短期視点でしか物事を見られない上司・・・といった構図だと思います。
その結果、私の忙しさは変わらず(いや、ますます忙しくなった!)、理不尽なことに目標を途中で上方修正され(たとえば10→15など)、その結果が14で終わったときは目標未達成の烙印を押されペナルティーを課せられる(他のチームは目標10のまま実績10で目標達成おめでとう!と褒められているのに!)。
本当に理不尽な目にたびたび遭いました。(後に、私が出世して上位リーダーに就いたあとはそういう社員はどんどんリストラ対象にしました)
・・・・・・・・・・・・
昨今、AIを使って業務効率を上げている企業も増えてきたと聞きました。
例えば、AIを使って資料作成が従来の1時間からわずか5分に短縮されたとします。
素晴らしい効率化です。
しかし、周りはこう期待します。
1時間が5分に短縮できるなら、あと11本作れるんじゃないか・・・と。
結果として、そこで空いた時間を同じ業務に使ってさらに多くの仕事をこなそうとし、結局、忙しさは従前と変わらない・・・という悲劇が起きます。
現場社員としてはAIが作業をこなし業務時間が短縮されたはずなのに、なぜか以前と変わらず忙しい・・・、むしろ、やることが増えたようにさえ感じる・・・となります。
急に時間ができても「その時間で次は何をすれば良いのか?」が明確になっていないと、リーダーはへんな不安を感じ、その不安を解消するために結局また新しい仕事を探し、
自ら忙しさに埋もれていくワナに嵌ります。
この負のループから抜け出すには、「効率化によって生まれた時間を何に使うのか?」を明確にする検討時間をしっかり持つことが必要です。
ラクになった・・・時間に余裕ができた・・・で終わらせるのではなく、その時間を活用して、リーダー自身、そして会社全体がより高いステージに進むための「新しい活動」を定義しておく必要があります。
皮肉なことですが、それを考えなければいけない役割を担っているのもまた「リーダー」自身です。
リーダーには、業務の効率化で「浮き時間をつくり」、そこでつくられた時間を活用して何をするのか?の「新しい目的意識を掲げる」力量が求められると思います。