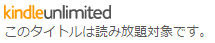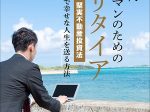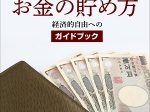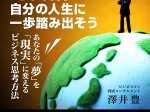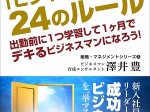葬儀や法事のときは、お坊さんを読んで読経してもらうのが通例です。
そのとき、お坊さんにはお礼として「布施」を渡しますが、この布施は仏教では別名「喜捨」とも呼ばれるそうです。
「喜捨」とは文字通り「喜んで捨てる」という意味です。
文字通り解釈するなら、 「喜んで捨てる」というのが喜捨=布施であって、イヤイヤ渋って出すとしたらそれは布施とは言えないことになります。
そういう背景を知ると、お布施を出すときは「喜捨」の心をもってお坊さんに渡すようにしよう・・・という気持ちになれます。
・・・・・・・・・・
昔はどんな町・村でも、自分の生活を省みずに仏法を説く僧(お坊さん)に「いつまでも元気で仏法を説いてもらいたい」・・・と感謝の気持ちを忘れなかった住民が多くいたと思います。
村の田畑で取れた米や野菜を喜んで持参するという風習があったのもやはり「感謝・喜捨」の気持ちがあったからだと思います。
それが一種の「布施」のあるべき姿だったのかもしれません。
「税金」であれば各人の収入によってその税額が決められ、本人の意向とは関係なく強制的に取り立てられます。
また、もしそこで納税を渋って払わなければ督促状で請求されますし、さらに延滞税が上乗せされたりします。
これに対して「布施」というのは出す側の人の自由意思で出されるものです。
決して強制されるものでもなければ、請求されて渋々支払うものではありません。
だからこそ、違う面で見れば、「布施」を頂戴する側であるお坊さんは、それに対するだけの仏法・読経を法要の際には心から誠実・真摯に提供ことが大切だと思います。
僧侶はまずわが身が仏教の布施の精神に則っているかどうかを立ち返って使命を自覚することが必要だとよく言われるそうですが、さもありなん・・・です。
その姿勢が薄れ、伝播されることが少なくなり、人々の気持ちにそうした想いが届かなくなってきたなら、門徒の寺離れが進み仏教が急速に衰退していくと思います。
昨今のお寺事情やお墓問題や法事問題などにはこうした時代の流れが少なからず存在しているのかもしれないですね。