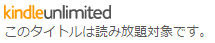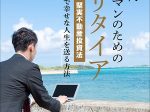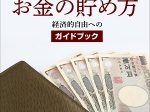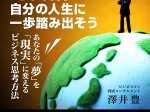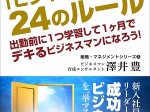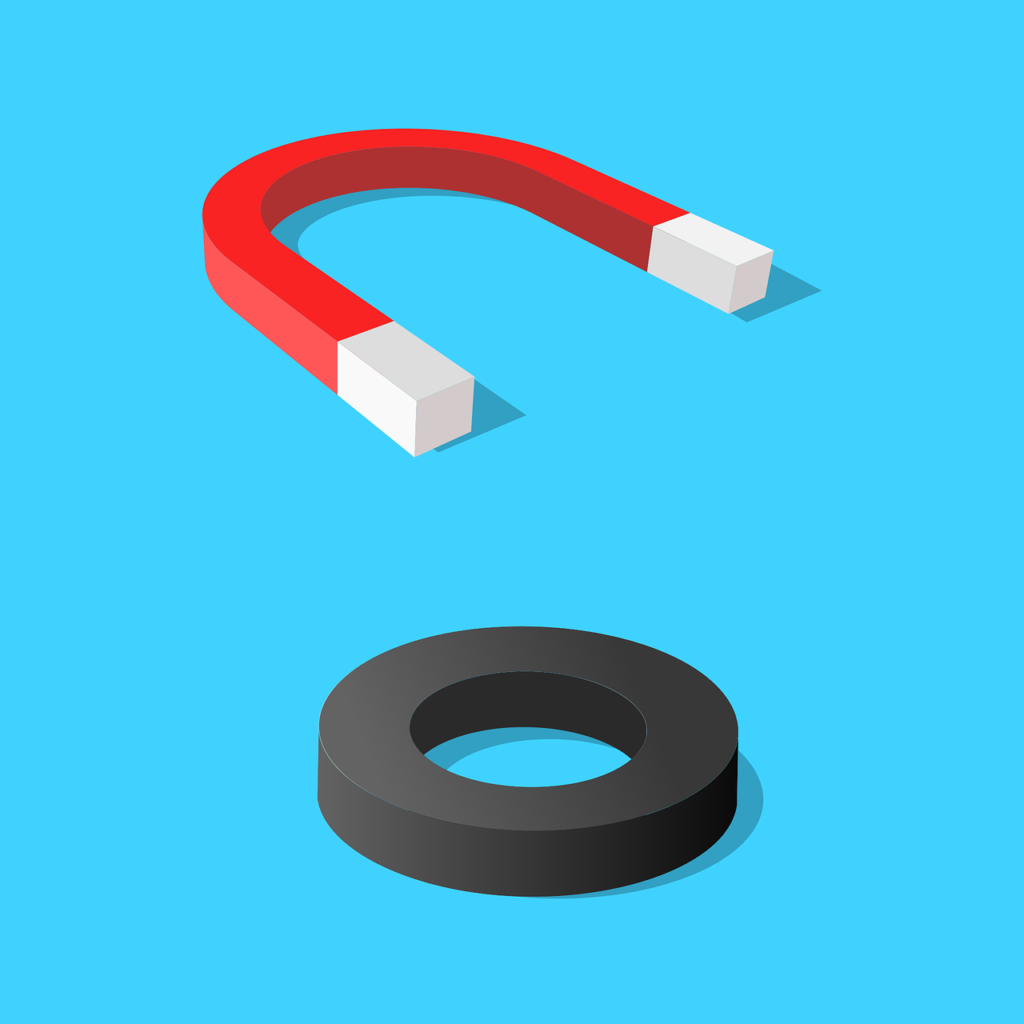
数学・計算では「公式」を「知ってるか?知らないか?」で大きく差がつきます。
「知っている」とすぐに「公式に当てはめて解く」ことができます。
「知らない」と解くのに時間がかかりますし、まずは公式を覚えることが必要だったりします。
たとえば、
Q. 直径10センチの円の面積はいくつ?
→ 公式を知っていたらすぐに計算できます。
知らないと「そんなことわかるか!」となります。
「公式を知る人」には数秒・数分でできてしまうことが「公式を知らない人」には何日・何カ月・何年かかってもできない・・・ことになります。
これが短期間で結果を出せるか/出せないか・・・の差です。
円の面積はこれでいいとしても、立方体の体積を求める公式はまた別の公式が必要になります。
学歴があっても現実社会で残念な人というのは「学歴という公式」で社会での成功が導けると勘違いしている人なのかもしれません。
用いる公式が間違っているなら、導き出される答えが間違っているのも当然です。
まるで「円の面積の求め方」で「立方体の体積も解ける」と勘違いしている感じです。
一方で、成功していく人というのは「社会的成功には学歴のような社会的閉鎖空間とは別の公式」が必要で、それをを覚え直すことが必要だ・・・とわかっている人です。
「社会は多様性」です。
だから「成功の公式」も業界や狙う位置に応じて無数に存在しているわけです。
一つの公式さえ覚えたらすべてうまくいく・・・というのは、社会的成功を成し遂げるにはあまりに幼稚な考え方です。
また、ありもしない「万能公式」を探そうとするのもナンセンスです。
ナンセンスな人がそんなありもしない万能公式を探している間にデキる人は「さまざまな公式」を覚え、適宜活用し、社会の荒波をうまく渡っていきます。
学校のテストで言えば、ヤマが当たった人と、実力のある人の違いみたいなもので、抜き打ちテストをすればすぐに正体が明らかになります。
テストの日が決まっている日の結果=学歴抜き打ちテスト=さまざまなことが起きる現実社会・・・です。
ある特定条件の時だけ通用する公式を持つのではなく、汎用性・将来性を持った公式を身につけることが大切です。
それに欠かせないことが「変化への適応力」と「先読み力」であり、それがたくさんの公式を作ることに役立つと思います。