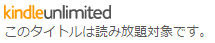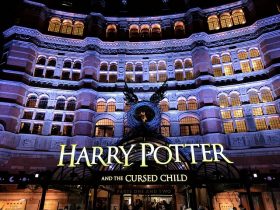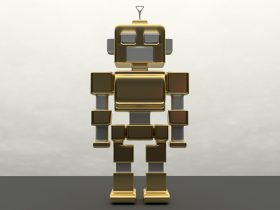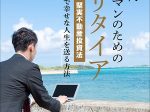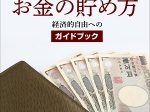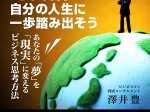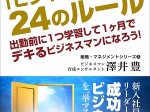鎌倉時代、上野国佐野(群馬県)という場所の山奥で猛吹雪となったある冬の夜。
佐野源左衛門という貧しい農民の家に、大雪で困った旅の僧が一夜の宿を求めます。
源左衛門は快く僧を家に迎え入れますが、貧乏のため囲炉裏の薪まで切らしていて、満足な食事を出すことができません。
そこで源左衛門は、丹精込めて育てていた梅、桜、松の盆栽の木を切って囲炉裏にくべて暖をとりてなします。
旅の僧は、そのおもてなしの心、また盆栽のたしなみや言葉遣いなどで、源左衛門のことを只者ではないと見抜きます。
実際、源左衛門はもともとは武士で、一門の者に本領を横取りされ農民になっていたのでした。
彼は、身は落ちぶれていても武士としての誇りは忘れておらず、古びた刀や鎧をきちんと保管しており、痩せ馬ではあるもののも馬も飼育していました。
それは、もし鎌倉幕府から呼び出しの号令があれば、真っ先に駆けつけるための心がけだったのです。
旅の僧は、その心がけにとても感心しました。
その数日後、鎌倉幕府から全国に召集があり、実際、源左衛門は旅の僧に語った言葉どおり、他の武士よりも早く鎌倉に一番乗りをします。
そのとき、源左衛門はあることに驚きます。
全国の武士に召集をかけた鎌倉幕府の前執権・北条時頼(ほうじょうときより)とは、先日家にやってきた旅の僧だったのです。
北条時頼は全国の御家人の様子を知るために出家して全国を旅していたのです。
源左衛門の「いざ鎌倉」の忠誠の精神が嘘偽りではないことを確認した北条時頼は、一族に奪われた旧領土を源左衛門に返還したうえ、梅、桜、松の鉢の木のおもてなしのお礼として、梅田庄、桜井庄、松井田庄という地名の領地を新たに源左衛門に与えたのでした。
以上が『鉢木』のおおまかな話で「いざ鎌倉!」の武士の精神の話ですが、この話の中心は何と言っても「秘蔵の鉢の木を切って火にくべる」ところです。
十分なモノが用意できなくても、十分な準備が整っていなくても、その場でできる限りの精一杯の心遣いをする。
それが、「おもてなし」の極意であることをこの話は語っていると思います。
高価なご馳走でなくても、豪華な設備でなくても、「おもてなし」というものは実現できることを意味していると思います。
最近はこうした「おもてなしの心」を忘れ、豪華絢爛でなければならない・・・という意識が先に立つ人も多いかもしれませんが、そこまでしなくても良いのがやはり「おもてなしの精神」だと思います。