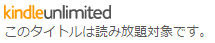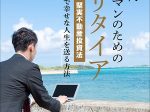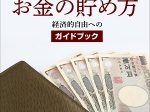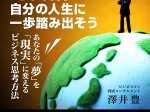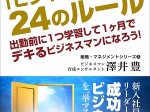多くの人が学んできたことは、ちょっと穿った見方をすれば「歯車養成のシステム」であり、将来的に「雇われること」を前提としている教育と言えるかもしれません。
「教育」は主な当事者の側から見れば「教わり育つ」ですが、副の当事者側から見れば「教え育てる」です。
主と副の当事者のどちらを重要視するかで見方が変わってきます(私は主のほうが大事だと思っています)。
多くの人は何となく「教育とは教え育てるもの」という発想をしがちですが、それは前述の「歯車養成システム」の影響から「雇われ脳」に陥っているのかもしれません。
「雇われ脳」の対義語は「経営者脳」です。
「経営者脳」は日本の教育で育まれることは難しいような気がします。
ノーベル賞を受賞した人たちも似たようなことをよく言っていました。
・・・・・・・・・・・・
「思考の浅い人」が「思考の深い人」をよく叩きます。
思考の浅い人のほうが数が多く、多数決の論理で「数が多いほうの勝ち」と言わんばかりに自分と反対の立場の人を叩くわけです。
それが適切な場合もありますが、必ずしもそうではありません。
未知なるモノを理解しようとせず、「あくまで自分のわかる範囲」で理解したつもりになって「可能性の世界」を頭ごなしに否定するようなパターンはうまくないと思います。
本当に賢い人は「可能性」を否定しません。
「自分にはまだ知らないことがある」と知っています。
「無知の知」です(ソクラテスです)。
未来は今の自分の想像を超えている、と思ったほうが正解です。
思考の浅い人は「雇われ脳」のタイプに多く、思考の深い人は「経営者脳」のタイプに多いような気がします。
ビジネスマン・経営者は「経営者脳」を持っている人が多いと思いますが、サラリーマンも意識をチェンジして「雇われ脳」から脱するほうが良いと思います。